“なりたい自分”に近づく! 介護職のための目標設定研修
1. なぜ目標が必要なのか?
目標があると仕事が変わる
仕事にやりがいが生まれる
目標があることで、「何のために働くのか」が明確になります。例えば、「利用者と1日1回は笑顔で会話する」といった目標を持つだけでも、日々の関わりに意味を見出すことができます。仕事が“ただの作業”ではなく、“誰かの役に立っている”という実感に変わるのです。やりがいは人それぞれですが、自分自身が目標を設定することで、そのやりがいに気づくきっかけになります。
成長が実感できるようになる
目標は、自分がどれだけ成長できたかを可視化するツールです。目の前の業務に追われていると、自分が変化していることに気づきにくいものですが、「先月は1人でできなかったことが、今月は1人でできた」というように、具体的な変化が見えると自信に繋がります。小さな達成の積み重ねが、自分の成長を感じる材料となり、次のチャレンジへとつながっていきます。
「なんとなく働く」からの脱却
目標がない状態では、毎日がルーティンになり、「ただ時間が過ぎていく」感覚になりがちです。しかし、自分で立てた目標があると、「今日は〇〇を意識してやろう」と1日の行動に目的が生まれます。すると、自分の仕事に主体性が生まれ、気づけば“受け身”から“前向き”な姿勢へと変化していることに気づきます。目標は、仕事に「意味」を与えてくれる大切な道しるべです。
目標を持たないと起こること
仕事が作業化し、マンネリに
目標を持たないまま仕事を続けていると、どうしても“慣れ”が先行し、毎日の業務がただの「作業」になってしまいます。最初は新鮮だった仕事も、次第に「またこれか」と感じるようになり、やりがいや楽しさが薄れていきます。これは仕事への興味がなくなったのではなく、目的が見えなくなってしまっただけ。目標があると、日々の仕事に小さな刺激や成長の視点を持てるようになります。
評価されにくく、自信が持てない
「一生懸命やっているのに評価されない」と感じることはありませんか?その背景には、目標が不明確なために「何をもって頑張っているか」が伝わりづらいという問題があります。明確な目標を持ち、それに取り組む姿勢が見えることで、上司や周囲も応援しやすくなります。また、自分自身も「ここまで頑張れた」と振り返ることで、自己評価にも自信が持てるようになります。
職員間で温度差が生じる
チームの中で目標意識に差があると、協力体制がうまくいかず、ギクシャクすることがあります。「自分だけ頑張っている」「あの人はいつも同じ」などの不満が生まれやすくなります。しかし、チーム全体が目標を持ち、それを共有し合う文化があれば、自然と応援し合える関係が築かれます。目標は、個人の成長だけでなく、チームの一体感を生むエネルギーでもあるのです。
2. 目標を立てる前に考えたいこと
自分の“今”を見つめる
できていること・できていないこと
目標を立てる前に、まずは「自分が今、何ができていて、何がまだ苦手なのか」を整理することが大切です。例えば、「報告・連絡・相談は意識してできているけど、記録がいつも遅れがち」など、自分の中で客観的に把握することで、自然と“伸ばしたいポイント”が見えてきます。得意なことを伸ばすのか、苦手を克服するのか。自分の“現在地”を知ることが、目標設定の第一歩です。
どんな時にやりがいを感じるか
仕事の中で「やってよかった」と思える瞬間は、人によって違います。例えば、利用者の笑顔にふれた時、同僚に「ありがとう」と言われた時、自分の提案が採用された時など、心が動いた経験を思い出してみましょう。そこに“自分が大切にしたいもの”が隠れていることがあります。やりがいを感じる場面を意識することで、「こういう場面をもっと増やしたい」という前向きな目標が生まれやすくなります。
苦手なことにどう向き合っているか
誰にでも苦手なことはありますが、それをどう捉え、どう向き合っているかが成長のカギです。「苦手だから避ける」のか、「少しずつ取り組んでいる」のかで、今後の目標の立て方も変わってきます。例えば、「人前で話すのは苦手だけど、毎朝の申し送りでは1つ伝える努力をしている」といった姿勢も立派なチャレンジです。自分なりに工夫してきたことや、今後取り組んでいきたい姿勢に目を向けましょう。
自分が目指したい姿とは?
どんな介護士になりたいか
「誰かの役に立ちたい」「頼りにされる存在になりたい」など、自分が思い描く“なりたい介護士像”は目標を考えるうえで大切なヒントになります。具体的な名前を挙げて、「○○先輩のように落ち着いて対応できる人になりたい」といった思いでも構いません。理想像がはっきりすると、「そのために今できること」を逆算して目標を立てることができ、目標に向かう道が具体的になります。
利用者にどんなふうに思われたいか
「この人が来ると安心する」「話しやすい」「信頼できる」——そんなふうに思われたいという願いは、介護職としてのやりがいにも直結します。どんな声をかけ、どんな関わりをしていけば、そう思ってもらえるのか。自分が目指す“印象”や“信頼のカタチ”を明確にすることで、日々のコミュニケーションやケアのあり方にも意識が向くようになります。
仲間からどんな存在として見られたいか
チームで働く介護の現場では、「仲間からどう見られたいか」も目標設定のヒントになります。たとえば、「あの人に相談すると安心できる」「落ち着いていて頼もしい」と思われるような存在を目指すのか、それとも「明るくて場を和ませてくれる人」なのか。自分が職場の中でどんな役割を果たしたいのかを考えることは、信頼関係の構築や職場全体の雰囲気づくりにもつながっていきます。
3. 目標の立て方と種類
日々の業務に直結する目標
「記録を○分以内に終える」などの具体行動
毎日の業務の中で、“具体的な行動”に焦点を当てた目標は実行に移しやすく、効果が見えやすいのが特徴です。例えば、「午後の記録を15時までに書く」「1日1回は必ず声掛けを意識して利用者と会話する」など、時間や回数などで明確にできる内容が理想です。こうした目標は達成の感覚を得やすく、毎日の仕事がただのルーティンではなく「意識して動いている」という自覚を育ててくれます。
ケアの質向上に関わる取り組み
「もっと丁寧なケアをしたい」「その人らしさを大切にしたい」――そんな思いを形にする目標も大切です。たとえば、「入浴介助の際、利用者がリラックスできるよう声かけを増やす」「排泄ケアで、肌の観察を習慣化する」など、小さな取り組みがケアの質を高めます。こうした目標は、自分のケアが利用者にどう伝わっているかを意識するきっかけになり、より深い介護の喜びを感じられるようになります。
利用者との関係づくりに関する目標
「もっと信頼関係を築きたい」「会話が弾むようになりたい」と感じている方には、コミュニケーションをテーマにした目標がおすすめです。例えば、「1日1回は利用者に“その人の過去”に関する話題を振ってみる」「いつも不機嫌な利用者に、毎回笑顔であいさつする」など、関係づくりに直結する行動を目標にします。結果がすぐに出なくても、少しずつ変化が感じられるようになるのがこのタイプの目標の魅力です。
自分の成長に関する目標
知識・技術を深める学習目標
日々の業務をこなしながら、少しずつ知識や技術を深める学習目標は、長い目で見たときの成長に繋がります。例えば、「毎月1冊、介護や認知症ケアの本を読む」「移乗介助について研修で学んだことを1つ実践する」といった形で、自分の“伸ばしたい力”を明確にすると良いでしょう。すぐに結果が出なくても、積み重ねが自信やスキルアップに繋がっていきます。
後輩やチームへの関わり方
経験を積んできた職員にとっては、後輩や同僚への関わり方も大切な成長のテーマです。例えば、「1週間に1回は後輩に声をかけて振り返りの時間をつくる」「自分が受けたアドバイスをチーム内で共有する」など、自分の経験を活かす形の目標が挙げられます。教えることは、自分自身の学びを深めることでもあります。こうした目標は、チーム全体の雰囲気づくりにも良い影響を与えます。
資格取得やリーダーへの準備
将来的にステップアップを目指している場合は、その準備となる目標を立ててみましょう。たとえば、「今年中に実務者研修を受講する」「リーダーの業務を1つ手伝ってみる」といった目標が考えられます。具体的な資格や役職だけでなく、「現場を広く見渡せる視点を持つ」「他部署との連携を意識する」など、内面的な成長も立派な目標になります。未来を見据えた小さな一歩が、大きな自信に変わっていきます。
4. 続けられる目標の工夫とポイント
「続けられる」ためのコツ
小さくていいから“できそう”と思えることから
目標は「大きく立てすぎない」ことが長続きのコツです。たとえば、「記録を毎日完璧に仕上げる」ではなく、「1日1回、意識して早めに記録する」といった小さな取り組みから始めると、達成感が得やすくなります。「できた!」という実感を積み重ねることで、もっとやってみようという気持ちが湧いてくるのです。小さな成功の積み重ねが、大きな変化につながります。
「毎日」よりも「週に3回」など柔軟に
完璧を目指しすぎると、できなかったときに「自分はダメだ」と感じてしまい、やる気が続かなくなることがあります。たとえば、「毎日必ず笑顔で挨拶する」と決めるのではなく、「週に3日は意識的に挨拶する」など、あらかじめ“ゆとり”のある目標にしておくことで、気持ちにも余裕が生まれます。継続できる目標は、「できなかった時も立て直せる」仕組みがあることがポイントです。
失敗しても“やめない”ことが成功のカギ
目標に取り組んでいると、うまくいかない日もあります。でも、そこで「やっぱり無理」と諦めるのではなく、「じゃあ明日はどうする?」と考え直せるかが大切です。目標は“達成すること”だけが目的ではなく、“目指して続けること”そのものに価値があります。途中でつまずいたとしても、立ち止まって見直すことで、次に進むヒントが得られるはずです。
周囲と一緒に取り組む
仲間に目標を話してみる
自分だけで抱えていると、目標はつい忘れてしまいがちです。思い切って同僚やリーダーに「今こういうことを頑張ろうと思ってる」と話すことで、意識も高まり、支援も得られやすくなります。周囲に話すことで「見られている」という良い緊張感も生まれ、継続への後押しになります。また、共通の目標があれば、お互いに励まし合える関係性も築けます。
一緒に振り返る時間を作る
一人で目標を振り返るのが難しい場合は、ペアやグループで定期的に「最近どう?」と話し合う時間を持つのも効果的です。「自分だけじゃなかった」「少しずつだけど前進してる」と感じられることで、継続する力になります。月1回でも「ちょっと振り返る時間」を設けることで、目標への意識がリセットされ、継続する意欲が高まります。
頑張りを認め合う風土が続ける力になる
目標を継続するためには、「頑張ったことを誰かに認めてもらえる」ことが大きな励みになります。「最近、記録が早くなったね」「利用者さんとの会話、増えたよね」など、小さな変化に気づいて言葉をかけてもらえると、「見てもらえてる」と実感できます。チーム全体でお互いを認め合える風土が、個人のやる気を引き出し、目標を続ける土台になります。
5. 成果を次のステップへつなげる
達成したときの振り返り方
「できたこと」を言語化する
目標を達成した時は、「何となくできた」ではなく、「どんな工夫をしたからできたのか」「何が良かったのか」を言葉にして整理することが大切です。例えば、「利用者の名前を呼んであいさつしたら、笑顔が増えた」と気づければ、それは大きな前進です。言語化することで、自分の成長が明確になり、同じような場面で再現しやすくなります。成長は“記録”や“振り返り”によって、自信ある行動に変わっていきます。
周囲に報告・共有する
目標の達成は、チームで共有することで自分だけでなく職場全体の活力にもなります。例えば、「今月は記録を遅れずに書くことを目標にして、だいぶ習慣づいてきました」と報告すれば、他の職員も「自分も何かやってみよう」と刺激を受けることがあります。上司やリーダーに伝えることで、適切な評価や次のステップへのアドバイスも得られます。共有は、自分の頑張りを“職場の力”に変える手段でもあります。
自分を素直に褒める
目標を達成できたら、「自分、よく頑張ったな」と素直に認めてあげましょう。特に介護の現場では、自分の頑張りを当たり前としてしまいがちですが、小さな積み重ねこそが本当に価値のあることです。「あの日は疲れていたけど、声掛けだけは意識した」など、日々の努力をしっかり振り返り、達成感を味わうことが、次の挑戦へのエネルギーになります。まずは自分が自分を大切にすることが、継続の原動力になります。
次の一歩をどう決めるか
新しい課題を見つける
目標を達成したら、終わりではなく「次は何に取り組もう?」と考えることが大切です。日々の業務の中で、「ここはまだ自信がない」「もう少しうまくやりたい」と感じる場面をメモしておくと、自然と次の課題が見えてきます。例えば、「もっと他部署と連携できるようになりたい」「ケアの記録だけでなく、観察の質も高めたい」など、自分なりの“新しいチャレンジ”が目標になります。
段階的にレベルアップする
いきなり大きな目標に挑戦するのではなく、段階的に目標のハードルを上げていくことで、無理なく成長できます。たとえば、最初は「1日1人に笑顔で声掛けする」、次は「1日3人に話しかけて会話を広げる」など、少しずつ難易度を上げるのがポイントです。こうしたステップアップの積み重ねが、自分でも気づかないうちに「頼れる存在」への道をつくってくれます。
チーム全体で成長を喜ぶ
目標達成は個人の成果であると同時に、チーム全体で喜び合える瞬間です。たとえば、「○○さんの声掛け、最近すごく丁寧になってるよね」と仲間に言われるだけでも、達成感は何倍にもなります。誰かの成功を一緒に喜び、自分の頑張りも受け入れてもらえる雰囲気は、職場全体を温かくします。目標を共有し、互いに成長を応援し合える環境づくりが、継続と向上の力になります。
まとめ:目標があるから成長できる!
目標は、自分らしく働くための“道しるべ”
• 目標があることで、日々の仕事に意味とやりがいが生まれます。
• 「なんとなくやる」から、「こうなりたいからやる」へ。
• それは、自分自身の成長にも、利用者へのより良いケアにもつながります。
“今の自分”を見つめて、“なりたい自分”を描く
• 得意・不得意、やりがいを感じる瞬間を振り返ることで、目標が見えてきます。
• 「どんな介護士になりたいか?」を考えることが、前向きな一歩に。
大きな目標より、“できそう”なことから始めよう
• 続けられる目標は、実現できる目標。
• 小さくても、一歩踏み出すことで見える景色が変わります。
• 完璧を目指さず、途中でつまずいても「やめない」ことが何より大切。
達成したら、自分を褒めて、次の一歩へ
• できたことを振り返り、言葉にして、自分の努力を認めましょう。
• 仲間に共有することで、お互いを励まし合える関係が生まれます。
• 次の目標は、今よりほんの少しだけ前に進むものでOK!
最後に:目標は“頑張る道具”じゃなく、“自分らしく働く地図”
目標を持つことは、「無理して頑張る」ことではなく、
「自分がどう働きたいか」に向き合うこと。
今日の気づきをヒントに、“自分らしい介護”への一歩を踏み出していきましょう!
おわりに
最後までお付き合い頂きありがとうございました
いかがだったでしょうか?
スライドの作成もやりやすい形にしてみました。
参考にして頂ければ幸いです。
参考になるかわかりませんが、自分が職場研修で使用したスライドも載せておきます。
ダウンロードはコチラから
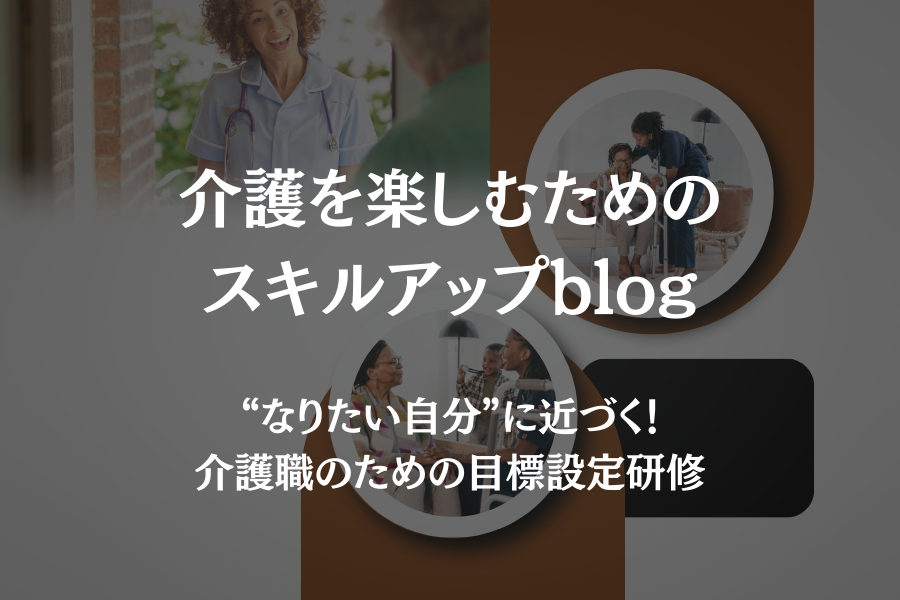


コメント